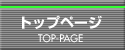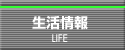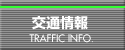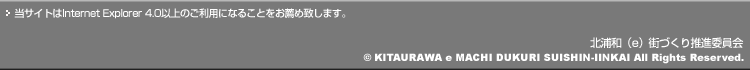神事に日時を合わせての旅は、風情もひとしおです。新春の伏見稲荷大社は、まず1月12日に奉射祭。本殿での祭典が行なわれた後、宮司が神矢を射て邪気や陰気を祓い陽気を迎えます。 神事に日時を合わせての旅は、風情もひとしおです。新春の伏見稲荷大社は、まず1月12日に奉射祭。本殿での祭典が行なわれた後、宮司が神矢を射て邪気や陰気を祓い陽気を迎えます。
そして2月は豆まきが行なわれる節分祭。さらに2月の初午の日(2008年は2月12日)に行なわれるのが、京洛初春第一の祭事といわれる初午大祭です。稲荷山の杉と椎の枝で作った“青山飾り”を飾り、参拝客には商売繁盛・家内安全の護符「しるしの杉」が配られます。
いにしえの京都の行事、風俗を今に伝える「枕草子」にも、著者である清少納言が初午詣に出かける様子が記されています。いわば初午詣は、昔から京都の人びとの「トレンド」だったといえるでしょう。
さて、時代ごとに「トレンド」が巻き起こった文化の中心地といえる京都ですが、ご存知のとおり明治時代になると「遷都」となり、首都が江戸(東京)に移りました。人口が流出し、このままでは京都の精神が失われてしまう、そう危惧した人びとの手で創られた神社があります。それが平安神宮です。
明治28年は、桓武天皇によって創られた「平安京」誕生から遷都1100年の年でした。その記念として、平安京大内裏の正庁、朝堂院を模して造られたのが平安神宮です。そのため祭神には平安京で過ごした最後の天皇、孝明天皇も合祀されています。訪れた人がまず息を呑むのは、高さ24.2メートルを誇る巨大な鳥居。そして平安時代の姿をそのままに再現した、正面に構える応天門。神社といえば「朱塗り」の建築の眩しさが特長ですが、平安神宮は桓武天皇1200年大祭のおりに塗り替え工事が行なわれたため、朱色がいっそう鮮やか。冬の晴れた日の青空とのコントラスト、その美しさは京都が培ってきた「美」の結晶といってもよいかもしれません。 |